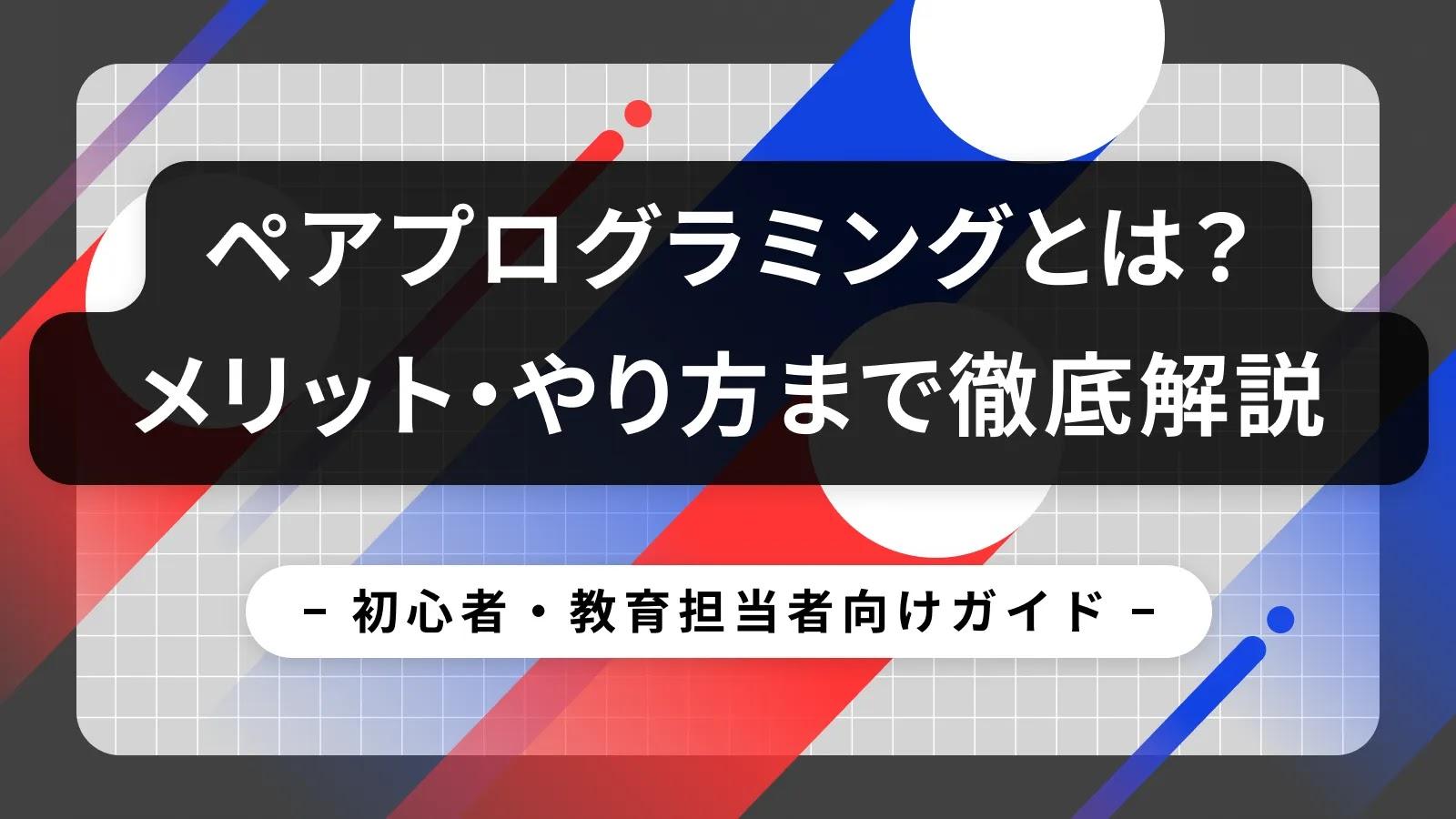LP制作の流れを徹底解説|依頼前に知っておきたい準備と注意点
- Web制作

目次
LP制作におけるスケジュール感と制作期間の目安
LP制作にはどの程度の制作期間が必要なのか?
LP制作の期間は、内容や体制によって大きく変わります。いわゆる要件によって変動するということです。
ただし、目安としては、簡易的な情報構造/構成がある場合かつ、素材提供もあるような状態であれば、2〜3週間ほどで可能です。しかし、しっかりと内容を作り込むケースでは1〜2ヶ月程度を見ておく必要があります。
- 構成の複雑さ(丁寧な競合調査などを行う場合)
- 原稿・画像などの素材準備ができているか
- 関係者のレビュー体制や、求める完成度
上記などによって、必要な制作期間は大きく変動することが考えられます。
LP制作を急いで作成したい時の注意点
「キャンペーンの開始日が迫っている」「急ぎでLPを立ち上げたい」といったケースは珍しくありません。
短期間でのLP制作は可能ですが、進め方を工夫しないと品質が下がったり、逆にスケジュールが延びてしまうこともあります。
以下のポイントを意識することで、スムーズかつ効果的に短納期のLPを完成させることができます。
ポイント【1】要件の優先順位を明確にしておく
→急ぎの制作では、「何を削れるか」ではなく「何を最優先で伝えるか」を先に決めることが重要な点です。
- 必須のコンテンツ
- 省略可能な要素
ポイント【2】テンプレート活用でスピードと品質を両立
ただし、品質を担保するためには最低限の確認フローを確保することも重要です。
社内調整と稟議の流れ
特に企業や自治体などでの制作では、担当者1人だけでは完結しないケースが多く、社内での稟議や上長・関連部署の承認が必要になります。
- 法務・コンプライアンスチェック
- ブランドガイドラインの確認
- 複数部署によるレビュー
といったプロセスがある場合は、制作期間とは別に社内調整の時間を見込んでおくことが重要です。
無理のないスケジュール設計を行うためにも、関係者の確認体制を事前に整理しておくことをおすすめします。
LP制作の流れを解説
LP制作における5段階の基本的な流れ(早見表)
LP制作の基本的な流れは以下の工程になります。

以下にて工程ごとにご説明いたします。
LP制作の最初のステップ 上流設計
ヒアリング
LP(ランディングページ)を外注する際、最初に行うのが「ヒアリング」です。これは単なる質問のやり取りではなく、貴社のビジネスや目的を深く理解し、「成果につながるページをどう作るか」を一緒に設計するための重要なステップです。
たとえば、以下のような内容をお伺いします。
- 誰に向けたLPか(ターゲット)
- 何を伝えたいか(サービス・商品の強み)
- どんな結果を期待しているか(KPIやゴール)
- 参考にしたいイメージ・競合サイト
- スケジュールや公開希望時期
このヒアリングの質が、その後の構成やデザイン、コピーの完成度を大きく左右します。逆に言えば、「うまく言語化できていない」「何を伝えればいいか分からない」という状態でも問題ありません。こちらから丁寧に質問し、必要な情報を引き出していきますのでご安心ください。
初回ヒアリングはオンラインで30分〜1時間程度。貴社の課題や目的を共有いただくだけで、最適なLPの方向性がクリアになります。
LP制作の要件定義
ヒアリングでお伺いした内容をもとに、「LPに何を載せるべきか」「どんな構成にするか」を整理するのがこの要件定義のフェーズです。言い換えれば、制作を進めるうえでの“設計図”をつくる作業といえます。
ここで明確にしていくのは、以下のような内容です。
- 目的やKPI
- お問い合わせ獲得/資料請求/購入促進など、目指す成果を明確に
- ターゲット像(ペルソナ)
- 想定するユーザーの年齢・職業・課題など
- 訴求ポイント
- サービスや商品の強み、他社との違い
- コンテンツ素材の有無
- 写真・テキスト・図解などを用意するか、こちらで制作するか
- スケジュールと予算感
- いつまでに、どの程度のボリュームで進めるか
これらを整理しておくことで、構成やデザイン、コピー作成の工程がスムーズに進みます。
ご希望があれば、要件定義書として簡易なドキュメントにまとめてご提出することも可能です。
LPの構成設計
構成設計では、要件定義で整理した情報をもとに、「どのような順序で、何を伝えるか?」を設計していきます。この設計が甘いと、いくらデザインやコピーが整っていても、ユーザーの心を動かすことはできません。
- ファーストビューで興味を惹く
- 共感を呼ぶ課題提起とサービスの解決策
- 詳細説明や実績紹介で納得感を与える
- よくある質問などで不安を払拭
- CTA(お問い合わせ・申し込みなど)へ自然に誘導
構成が決まった段階で、ワイヤーフレーム(画面の設計図)として可視化し、共有させていただきます。
この段階で「ここに実績を入れたい」「もう少し簡潔に」などのご要望を反映できますので、安心してお任せください。
LP制作のデザイン制作工程
ヒアリング内容の確認
構成などの上流の要件が固まったら、次はビジュアル面の設計作業に入ります。
具体的には以下のような形で確認を行います。
- 目的やターゲットの確認(KPIの確認)
- 訴求ポイントやコンテンツの方向性
- 構成イメージや参考サイトの共有
- 素材の有無、提出方法、納期などの実務的項目
ヒアリング直後にすぐ制作に入るのではなく、一度整理された情報を見ていただくことで、クライアント様の頭の中もクリアになります。
「少しニュアンスが違うな」「ここはもっと強調したい」など、修正や追加のご要望があればこの段階で遠慮なくお伝えください。
初めての外注で不安な方にも、「きちんと伝わっているか」を確認する工程を挟むことで、安心して次のステップへ進んでいただけます。
ブランド定義(ブランドアーキタイプとブランド)
ヒアリング内容の確認が完了したら、LP制作において重要な「ブランド定義」の工程に入ります。この工程では、お客様が商品やサービスに抱く印象や感情を統一するための基盤を構築します。
ブランドアーキタイプの選定
ブランドアーキタイプとは、ブランドの「人格」や「性格」を12のタイプに分類したマーケティング手法です。
例えば
- 支配者(Ruler):権威性や信頼感を重視するブランド
- 賢者(Sage):専門性や知識を前面に出すブランド
- 無邪気な人(Innocent):シンプルで親しみやすいブランド
- 英雄(Hero):挑戦や成果を重視するブランド
LPのターゲットユーザーに最も響くアーキタイプを選定することで、デザインやコピーライティングの方向性が明確になります。
ブランドイメージの具体化
アーキタイプが決まったら、以下の要素を具体的に定義します
- カラーパレット:ブランドを象徴する色彩設計
- フォント・タイポグラフィ:文字の印象や読みやすさ
- トーン&マナー:文章の語調や表現スタイル
- ビジュアル要素:写真やイラストの方向性
この段階で丁寧にブランド定義を行うことで、LP全体に一貫性が生まれ、ユーザーにとって記憶に残りやすいページに仕上がります。また、今後の広告運用や他のマーケティング施策でも活用できる資産となるため、LP制作の流れの中でも特に重要な工程といえます。
LPのファーストビューの作成&提案
LP全体の方向性と訴求軸が定まったら、いよいよファーストビュー(FV)の制作に入ります。FVは、ユーザーが最初に目にする領域であり、ブランドの第一印象を左右する重要な要素です。
限られた表示領域の中で、ターゲットの共感を得ながら、サービス・商品の魅力を簡潔かつ力強く伝えるため、以下の要素をバランスよく構築します。
ファーストビューに含めるべき要素
- キャッチコピー:ユーザーの課題や欲求に即したメッセージで興味を引きます。
- キービジュアル:ブランドトーンと一致した写真やイラストで印象づけを行います。
- CTA(Call to Action)ボタン:「資料請求」「お問い合わせ」など行動への導線を明確に提示します。
提案の進め方と注意点
ファーストビューの提案では、ユーザー視点とブランド戦略の両立が重要です。見た目の美しさだけでなく、ターゲットに刺さる構成かどうかを意識して進めていきます。
- 構成案の提示
- キャッチコピー、ビジュアル、CTAボタンを含んだレイアウト案(ワイヤーフレームなど)を共有し、全体の設計意図を明確に伝えます。
- 意図の共有とすり合わせ
- 「なぜこの構成なのか」「どの訴求軸がベースになっているか」を簡潔に説明し、クライアントと方向性の一致を確認します。
- 修正対応の進め方
- 提案後のフィードバックに応じて、コピーやデザインの調整を行います。ターゲットやCV導線を軸に判断することで、好みに流されすぎず、成果につながる設計を維持できます。
進行にあたって特に注意したいのは、情報を盛り込みすぎないことです。訴求軸が多すぎるとユーザーの理解を妨げるだけでなく、印象もぼやけてしまいます。また、スマートフォン表示時にファーストビューが途切れると、CTAの効果が発揮されず、CVに影響を与える可能性があります。ブランドのトーンやイメージとのズレにも気を配りながら、細部の設計まで整合性を意識することが、LP全体の品質につながります。
LP全体の制作
ファーストビューの方向性が決定したら、LP全体の制作工程に移ります。ここでは、ユーザーがファーストビューから最終的なコンバージョンまでスムーズに導かれるよう、全体のストーリー設計と各セクションのデザインを進めていきます。
全体構成の設計アプローチ
LP制作では、ユーザーの心理的な流れに沿った構成が重要です。ファーストビューで興味を引いた後、課題提起、解決策の提示、信頼性の担保、行動促進という一連の流れを意識して各セクションを配置します。構成設計で決定した要素を、実際のデザインとして具現化していく段階です。
各セクションの制作ポイント
LP全体の制作では、以下の要素を統一感を持って表現していきます。
- 課題・共感セクション:ターゲットの悩みや課題を具体化し、共感を生む構成
- 解決策・商品紹介:サービスや商品の特徴・メリットを分かりやすく訴求
- 実績・事例紹介:信頼性を高める導入事例やお客様の声
- 料金・プラン:明確で比較しやすい価格設定の提示
- FAQ・不安解消:よくある質問への回答で購入障壁を取り除く
デザインの一貫性と最適化
全体制作では、ファーストビューで決定したブランドトーンやビジュアル要素を各セクションに一貫して適用します。カラーパレット、フォント、余白の使い方などを統一することで、プロフェッショナルな印象を維持できます。
また、各セクション間の視線誘導も重要な要素です。ユーザーが自然に下へスクロールしたくなるような構成や、重要な情報へ適切に注意を向けさせるレイアウトを心がけます。スマートフォンでの表示も常に確認しながら、デバイスを問わず最適な体験を提供できるよう調整していきます。
LP制作の実装工程
実装・テスト工程
完成したデザインをもとに、HTML/CSS/JavaScriptなどを用いてコーディングを行います。ページ表示速度やモバイル最適化、アクセシビリティなどの観点から、ユーザーにとってストレスのない閲覧体験を提供することが求められます。また、リリース前にはリンクチェックやデバイス別表示確認などのテスト工程も必須です。
CMSやフォーム連携
LPによってはCMS(コンテンツ管理システム)との連携や、フォームの設置が必要となる場合があります。例えば、資料請求フォームや問い合わせフォームが設置されるケースでは、メール通知設定やスパム対策、DBへの情報格納などの技術要件を満たす設計が求められます。
納品・公開・運用の工程
最終チェックと公開
制作が完了したら、表示崩れやリンク切れがないかを全ページ確認し、内容に誤りがないかをチェックします。また、計測タグ(GA4やGTM)の実装や、リリース作業の手順書確認など、公開前にやるべきことは様々あります。これらの確認が完了して初めて、本番公開となります。
マニュアルの準備
特にCMSと連動するLPの場合は、更新方法や注意事項を記載した運用マニュアルを作成することで、社内メンバーが迷わず運用を行えるようになります。保守対応の範囲や問い合わせフローなども明示しておくと、社内のトラブル対応もスムーズになります。
納品作業
納品方法は主に2通りあります。 「素材納品」の場合は、HTML・画像・資料などをパッケージ化して引き渡します。
「本番公開まで依頼する場合」は、制作側がCMS登録やタグ設置などを含めて公開作業まで対応します。
どちらの場合も、納品内容のリストや確認用のチェック項目を添えることで、運用や社内共有がスムーズになります。
LP運用の準備
リリース後は広告運用やLP改善のフェーズに移ります。特にWeb広告と連携する場合、LPのクリエイティブごとにパフォーマンスを計測できるよう、パラメータ設計やABテストの準備が必要です。改善の余地を前提にした設計・運用こそが、LPの成果最大化に寄与します。
外注する際の注意点
準備すべき資料
外注時には、依頼の背景・目的・目標、社内体制、過去の取り組み、競合事例、自社の強みなどを資料としてまとめておくとスムーズです。これにより、制作側の理解が深まり、ズレの少ない提案が期待できます。
依頼先とのやりとりのポイント
制作会社とのやりとりでは、「返答スピード」「意思決定の速さ」「資料の出し方」などがプロジェクトの進行速度と品質に直結します。また、契約段階では納品範囲や成果物の定義、修正回数、運用支援の有無などを明記することも重要です。
よくある失敗とその回避策
よくある失敗として、「目的が曖昧なまま進行」「素材や原稿の準備が遅れる」「修正が多発して納期遅延」などが挙げられます。これらは事前準備と合意形成、スケジュール管理によって予防可能です。最初に「目的とゴール」を明確化することが、失敗を防ぐ第一歩となります。
LP制作のポイント
LP制作では、各工程を順に進めるだけでなく、「全体を通じた視点」が成果に大きく影響します。特に重要となる3つのポイントがあります。
①目的とゴールを常に意識する
どれだけデザイン性が高くても、ビジネス的な成果につながらなければLPの目的は達成できません。制作過程の中で迷った際は、常に「このLPの目的は何か(例:問い合わせ数の増加)」という原点に立ち返り、ユーザーにとってわかりやすく・行動しやすい構成になっているかを見直すことが大切です。
②ユーザー視点での導線設計
ユーザーが「自然と情報を理解し」「納得して行動できる」ように、コンテンツ配置やCTA(ボタン)導線を意識的に設計することが成果に直結します。特にスマートフォンユーザーにとってのストレスを最小限にするUI設計も、成果改善の鍵となります。
③改善前提で設計する
LPは公開して終わりではなく、スタート地点です。初期段階で仮説ベースの構成を作った後は、実際のアクセス・CVデータをもとに、継続的に改善を行うサイクルが重要です。計測環境の整備(GA・GTM・ABテストなど)を含め、改善前提で設計しておくことで、スピーディなPDCAが可能になります。
このように、個別の制作工程だけでなく、成果につながるための全体設計を意識することが、LP制作を成功に導くポイントとなります。
まとめ
LP制作は、単なるページ制作ではなく「成果につながる体験設計」です。 ヒアリングから運用までの各工程に目的があり、それぞれが密接に連動しています。
事前の準備とパートナー選定が成否を分けるため、自社に合った進め方を計画的に検討しましょう。
弊社では、「目的設計〜制作〜運用改善」までを一貫してご支援しています。まずは、お気軽にご相談ください。
「LP制作の流れを徹底解説|依頼前に知っておきたい準備と注意点」
の詳細が気になる方は、
お気軽にお問い合わせください

Y's Blog 編集部